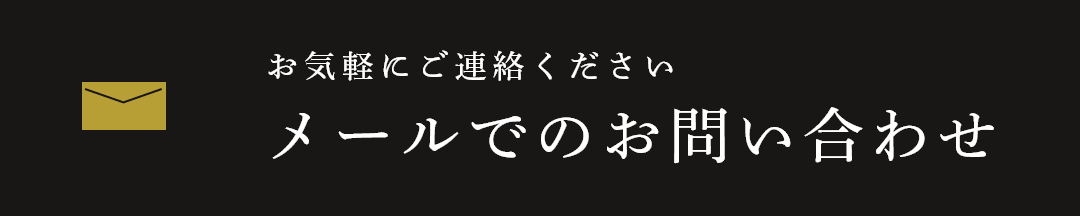-
2021.06.01
【消費者契約法】患者都合による治療中断の場合に、治療費の一部返還を認めた裁判例

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
今回は、インプラント施術の治療契約において、患者都合による治療中断の場合には治療費の返還はしない旨の条項(本件不返還条項)が定められていたが、契約を締結し、治療費を支払った後、インプラント施術前に、患者が亡くなりったため、相続人らが本件不返還条項は消費者契約法第10条により無効であるとして、不当利得返還請求権に基づき、治療費の返還を求めた裁判例(津地裁四日市支部令和2年8月31日判決)をご紹介させていただきます。
■消費者契約法第10条
同条後段には、「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と定められています。
民法第1条2項の規定は、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と定めた信義則の規定です。
■最高裁平成23年7月15日判決
消費者契約法10条にいう、条項が信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか否かの判断方法については、最高裁判例があり、「消費者契約法の趣旨、目的に照らし、当該条項の性質、契約が成立するに至った経緯、消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を総合考量して判断されるべきである。」とされています。
■津地裁四日市支部令和2年8月31日判決の骨子
まず当該裁判例は、本件不返還条項は、履行の割合に応じて報酬を請求することができるとする民法656条、648条3項に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項としました。
また、上記最高裁判例を引用した上で、次の理由から、本件不返還条項は、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するとして、消費者契約法第10条により無効であると判示しました。
・本件不返還条項は、施術が行われることなく終了しても、治療費全額の返還をしないというものであり、治療費の対価性を損なう規定となっていること。
・インプラント施術は身体的侵襲を伴うものであるから、治療は患者の意思に基づくものでなければならないところ、本件不返還条項によって、患者が治療を中断等する機会を制限するものであること。
・本件不返還条項は、承諾書に不動文字で記載されているもので、患者との個別交渉により合意されたものではないこと。
・患者が約3ヶ月ぶりに受診し、初めてインプラント契約が検討されたその日のうちに、契約締結に至っていること。
・患者も同伴者いずれも、80歳を超える高齢であったこと。
■不当利得の額
そして、当該裁判例は、見積もりの内容も踏まえると、予定されていた治療の大部分は未だ履行されていなかったと言わざるを得ないが、他方、仮義歯の作成及び調整、口腔内の観察も、インプラント治療において必要な手順であると認められ、4分の1程度は既に履行されていたとして、治療費264万6000円×3/4=総額198万4500円の返還を認めました。
-
2021.05.26
【消費者契約法】製品性能の不実告知があったとして、売買契約の取消が認められた裁判例

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
今回は、軽自動車の売買契約において、カタログの表示又は販売店の従業員の説明により重要事項である車両の燃費値について不実告知があったとして、消費者契約法4条1項による取消しが認められた裁判例(大阪地裁令和3年1月29日判決)を紹介させていただきます。
■事案の概要
三菱自動車等が、軽自動車のカタログ等に、「国交省の定める測定方法等による燃費性能」よりも優れた燃費性能を表示させた上で、販売店らをして、原告らに対して軽自動車を販売させたとして、車両に係る各売買契約を消費者契約法4条1項1号(不実告知)に基づいて取り消したなどと主張した事案です。
■不実告知による取消の要件
消費者契約法4条1項1号は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について、事実と異なることを告げたこと(不実告知)により、消費者が告知された内容を事実であると誤認し、それによって消費者契約の申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができると規定しています。
その要件を整理すると、次の通りとなります。
①事業者と消費者との間の契約であること(消費者契約該当性)。
②事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不実告知をしたか(勧誘及び不実告知該当性)。
③告知された内容は、重要事項に当たるか(重要事項該当性)。
④消費者が告知された内容を真実であると誤認したか、不実告知と誤認、誤認と消費者契約の申込みの意思表示との各間に因果関係があるか(因果関係の有無)。■ ①消費者契約
消費者契約法2条1項の「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)をいい、個人事業者であっても、事業としてでもなく、事業のためではない目的のために契約の当事者となる場合には、「消費者」となり得ます。
原告の一人であるJは個人事業主でしたが、主にその妻が日常の家事に使用するため、車両(サクラピンクメタリック色)を購入したことが認められ、自らの事業として又は自らの事業のために当該車両を購入したものとは認められないから、Jは、当該車両の売買契約において、「消費者」に該当するというべきであると判示されています。
■ ②勧誘及び不実告知
消費者契約法4条1項1号の「勧誘」とは、事業者が消費者に対し、消費者契約の締結に際し、消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の消費者契約の締結に向けた働きかけを行うことをいい、事業者が、その記載内容全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的に認識し得るような媒体により不特定多数の消費者に向けて働きかけを行う場合もこれに含まれます。
販売店らによるカタログの交付またはその従業員による説明は、同号の「勧誘」に当たるものと認められます。
また、カタログ等の「燃料消費率(国土交通省審査値)」の表示は、国土交通省の定める測定方法による算出値であるということを意味するものであるところ、国土交通省の定める測定方法による算出値ではないのに同測定方法による算出値であるかのように表示し、かつ、実際の国土交通省の定める測定方法による算出値よりも優良な数値を表示した点において、事実と異なるものであり、カタログ等の表示並びにこれを前提とした販売店らの従業員による説明を確認又は理解した者は、表示された値が国土交通省の定める測定方法による算出値であり、かつ、実際の算出値よりも優良な数値であることについて、事実であるとの誤認を生じさせるものというべきであるから、不実告知に当たると認められます。
■ ③重要事項
消費者契約法4条1項1号の「重要事項」とは、消費者契約に係る「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」(同条4項1号)等であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの(同項柱書)をいいます。
ここで「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」とは、契約締結の時点における社会通念に照らし、その契約を締結しようとする一般的・平均的な消費者が契約を締結するか否かについて、その判断を左右すると客観的に認められるような契約についての基本的事項をいいます。
そして、当該事案において、不実告知の対象事項は、車両の燃費値という「質」に関わるものであるところ、車両の燃費値は、軽自動車を購入しようとする消費者にとって、経済的な観点のみならず、環境問題への配慮がされた車両か否かという売買において購入の一つの重要な要素であり、事業者である三菱自動車おいても、目標燃費値を達成することが車両の売上げ増に直結するものであるとして、車両の開発が行われていたことが認められます。
これらの事情からすると車両の燃費値は、車両の売買契約を締結しようとする一般的・平均的な消費者が車両の売買契約を締結するか否かの判断に通常影響を左右すると客観的に認められるような車両の売買契約についての基本的事項に当たるものといえ、「重要事項」に当たるものと認められています。
■ ④因果関係
原告ら(一部を除く)は、販売店らから交付されたカタログ等又は被告販売店らの従業員の説明により、車両の燃費値が、国土交通省の定める測定方法による算出値であり、かつ、実際の算出値よりも優良な数値であることについて不実告知を受け、この内容を真実であると誤認したことが認められ、これによって車両の売買契約を締結したものと認められています。
-
2021.05.18
【建築トラブル】施工業者が破産した場合、どうする?

虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
最近も、アパートの階段崩落事故に関連して、施工業者が破産しましたが、施工業者(請負人)が破産して、建築工事がストップしてしまうことは度々起こることででして、私も相談を受けることがあります。
思いがけず、このような事態に陥って、お困りの注文者の方もいらっしゃるのでしょうから、今回は、施工業者が破産した場合の対応方について、ご説明させていただきます。
■「住宅完成保証制度」加入の有無の確認
「住宅完成保証制度」とは、施工業者が破産し工事を継続できなくなった場合に、住宅の完成に向けた工事費用や破産などにより戻ってこないお金(前払金等)の損失を保証したり、引き継ぎ業者をあっせんすることができる任意加入の保証制度です。
破産した施工業者がこの保険に加入していた場合には、その保険金により救済を受けられる場合がありますので、まず、この点を確認してください。
ただし、保証限度額が定められていたり、増嵩工事費用(未履行部分の工事を別の業者が代わりに施工した場合で、手戻り工事費や既施工部分の検査などを行う費用)の限度額が定められており、全額の保証を受けられるとは限りません。
なお、「住宅完成保証制度」と「住宅瑕疵担保責任保険」とは、別のものですので、注意が必要です。
後者の「住宅瑕疵担保責任保険」は、引き渡された新築住宅に特定の瑕疵があった場合に、補修等を行った施工業者や住宅販売業者に保険金が支払われる制度です。施工業者が破産した場合に、工事を続行するためにこの保険制度を利用することはできません。
■「住宅完成保証制度」に加入している場合の注意点
一般的に、次のような事実が発生したときには、発注者は、保険会社に対し、遅滞なく、通知することが求められています。
・建築工事の全部または一部の施工の中止を知ったとき。
・施工業者が倒産等、建築工事が継続できなくなる事実が発生したことを知ったとき。
・施工業者につき、破産、民事再生、会社更生手続開始の申し立てがあったことを知ったとき。
・発注者が、建築工事請負契約を解除しようとするとき(書面での通知)。
正当な理由なく、これら通知義務を履行しないと、保険会社による保証債務の履行を受けられなくなる場合がありますので、注意が必要です。
また、施工業者が倒産等した場合、保険会社(の依頼を受けた鑑定人)が、当初締結した請負金額に係る見積単価に基づき、出来高の算定を行うことになります。
■その他、初動で行うべきこと
(工事の進捗状況の撮影)
後述の通り、破産管財人が請負契約を解除する場合には、工事の出来高の査定が必要不可欠になりますので、速やかに、工事現場で、工事の進捗状況を詳細に撮影し、証拠を保全すべきです。(出来高の査定)
また、施工業者の従業員や、他の専門業者の協力を得て、出来高の査定を行ってください。なお、工事現場の占有は施工業者(破産後は、破産管財人)にあると考えられますので、工事現場に立ち入る場合には、破産管財人に立ち会ってもらうか、破産管財人の同意を得て行うべきです。
(建築中の建物の保全)
工事途中の建物を長期間放置しておくと、風雨によって建物が劣化してしまうような場合には、応急措置としてブルーシートをかけるなどの保全行為については、損害の拡大を防ぐために許されると考えられますが、念のため、破産管財人の了承を得て行ってください。■破産管財人からの解除
工事が未完の場合、基本的に、施工業者の破産管財人は、請負契約を解除するか、あるいは残りの工事を履行して、注文者に対し、残りの請負代金を請求するか、選ぶことができます(破産法53条1項)。ただし、その工事が破産をした施工業者にしか完成することができない工事の場合には、同条は適用されません(最高裁昭和62年11月26日判決) 。
破産管財人としては、工事を継続する方が支払う経費よりも、入ってくる請負残代金の方が多く、破産財団の増殖が見込める場合は、工事の継続を選択し、工事の完成を目指すことになります。
もっとも、一般的には、契約不適合や、事故発生時の労災補償の問題などから、工事継続は難しく、解除を選択することが多いと考えられます。
他方、注文者は、破産管財人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に、請負契約を解除するか、それとも工事を遂行して請負代金を請求するのか確答するよう催告することができます。これは、どちらかを選ぶよう催告することであり、残工事を履行せよと催告したり、請負契約を解除せよと催告することではありません。
破産管財人が、その期間内に確答しないときは、請負契約は解除したものとみなされます(同条2項)。
■請負契約が解除された場合の取扱
(出来高が前払金よりも多い場合)
契約が解除されたとき、施工業者が既にした工事のうち可分な部分の給付によっても、注文者が利益を受けるときは、その部分は仕事の完成とみなされます。この場合、破産管財人は、注文者に対し、注文者が受ける利益の割合に応じて残代金を請求することができます(改正民法634条)。
(前払金が出来高よりも多い場合)
他方、出来高を査定した結果、注文者が施工業者に対し支払っていた前払金の方が、出来高よりも多い場合は、注文者は、破産財団に対し、その超過額について、施工業者に支払った代金が破産財団中に現存するときは、その返還を求めることができますし、現存しないときは、その価額について、財団債権として保護され(破産法54条2項)、破産債権よりも優先して弁済を受けることができます。
ただし、財団債権として保護されるのは、あくまで出来高よりも多く支払った前払金の超過額のみです。
破産管財人により、契約が解除された場合、例えば次のような、注文者が被った損害は、破産債権として権利行使することしかできません(同条1項)。
・建物や設備の劣化を防ぐため、注文者が支出した工事の保全費用
・他の施工業者に、残りの工事を引き継がせたことにより、総額の工事費用が増えた分
・工事が遅れたことによる損害破産債権の配当が受けられるかは、財団財産がどれだけ形成されるかによりますが、実際には、全く配当を受けられないか、配当を受けられても、破産管財人により認容された破産債権額の数パーセント程度のことがほとんどなので、あてにはせず、いくらかでも配当を受けられたら儲けもの程度に考えておいた方がよいでしょう。
■工事出来高の査定方法
工事の出来高は、工事代金の内訳明細書や、工程表、その他関係資料等を参考に、工事費目ごとの進捗率に応じて算定します。
破産管財人としては、破産会社の従業員などの協力を得て、工事の出来高の査定をしていくことになります。
これに対し、注文者からは、引継業者が見積もった残工事費用を、当初の工事代金から控除して、既施工部分の現在価値を出来高とすべきとする主張をすることもありますが、このような主張は、本来、破産債権となるにすぎない増加工事費用を相殺的処理により優先弁済受けるのと同様の処理になりますので、破産管財人により認められないでしょう。
■違約金の請求・相殺の可否
破産管財人により、破産法53条に基づき、請負契約が解除された場合、注文者は、破産管財人(破産財団)に対し、請負契約書の違約金条項に基づき、違約金を請求することができるでしょうか?
裁判実務では、違約金請求ができないとする裁判例が多く存在します(東京地裁平成27年6月12日判決、札幌高裁平成25年8月22日判決等)。
同条による解除権は、法によって破産管財人に与えられた特別の法定解除権であり、違約金条項の適用はないと考えられるからです。
また、仮に、違約金が発生する場合でも、その違約金は、破産手続開始決定後に発生した破産債権ですので(54条1項)、注文者が、これと請負代金支払債務などと相殺主張することはできない(67条1項)と考えられます。
■下請業者や設備業者が所有権を主張する場合
工材や設備を納品した下請業者や設備業者が、破産した施工業者から代金が支払われていないことから、これらの所有権を主張して張り紙をしたりする場合があります。
この点、いったん納品した以上、これらの所有権や占有は、施工業者に移転しており、下請業者らが、同意なく引き揚げてくることは自力救済行為として許されません。
もっとも、設備など動産の売主には、動産売買の先取特権が認められ(民法321条)、破産法上、別除権として保護され(破産法2条9号)、破産手続きによらずして、破産管財人の同意を得て、引き揚げることができますので(同法65条)、破産管財人と下請業者らとの話し合い次第となります。
ただし、下請業者らは、既に木材等が建物として組み上げられた場合、施工業者の注文者に対する請負代金債権について、原則として、物上代位権を行使することはできません。
例外的に、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を当該動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、その部分の請負代金債権に対して物上代位権を行使することができます(最高裁平成10年12月18日決定)。
また、下請業者らと、注文者はとの間には、直接の契約関係がなく、下請業者らは、注文者に対し、直接、下請代金を請求することはできません。
■残りの工事の進め方
破産管財人により請負契約が解除された場合、残りの工事を施工してもらえる業者を探し、改めて請負契約を締結することになります。
この場合、それまで工事を進めていた下請業者などが信頼できるところであれば、そこと直接契約を締結したり、破産した施工業者の社員(現場監督)と直接、工事監督ないしコンサルティング契約を締結したり、足場などのリース業者と直接リース契約を締結したりして、いったん中断した工事を継続する方が、関係者が事情を知っていて、時間もコストも節約することができる場合があります。
実際に、そのようにして、リカバリーされる方もいらっしゃいます。
-
2021.04.13
【クーリング・オフ】法人や事業者はできない?
虎ノ門桜法律事務所の代表弁護士伊澤大輔です。
中小企業庁のホームページでも、「事業者間の取引に関しては、クーリング・オフは適用されません」と説明されています。それは基本的には正しいですが、正確ではないかもしれません。

■根拠条文
訪問販売などについては、特定商取引法において、クーリング・オフの制度が定められています(9条)。
もっとも、「営業のためにもしくは営業として締結するもの」については、特定商取引法のすべての条項の適用が除外され、クーリング・オフも適用されません(26条1項1号)。
この適用除外の規定があることから、「事業者間の取引に関しては、クーリング・オフは適用されません」と説明されているわけです。
■適用除外の解釈
しかし、同号の趣旨は、契約の目的・内容が営業のためのものである場合に特定商取引法が適用されないという趣旨であって、契約の相手方の属性が事業者や法人である場合を一律に適用除外とするものではありません。
例えば、法人や事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として特定商取引法が適用され、クーリング・オフもできる場合があるのです。
特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、特定商取引法が適用される可能性が高いです。
令和2年3月31日付通達でも、以上のように説明されています。
「営業のためにもしくは営業として締結するもの」にあたるか否かは、形式的に、契約書上の当事者が誰かではなく、実質的に事業者の営業の目的との関連、契約の目的・内容・用途、使用形態、支払が営業経費か個人の家計からか、反復継続した取引か、事業者の事業規模などにより判断されるべきものです。
■クーリング・オフを認めた裁判例
法人や事業者が契約当事者の場合にも、クーリング・オフを認めた裁判例として、以下のものがあります。
【大阪高裁平成15年7月30日判決】
消火器の訪問販売業者が、自動車販売会社に対し、消火器38本を販売した事案につき、原告会社は、自動車の販売等を業とする会社であって、消火器を営業の対象とする会社ではないから、当該契約は「営業のためにもしくは営業として締結するもの」ということはできないとして、クーリング・オフを認めています。
【名古屋高裁平成19年11月19日判決】
個人で印刷画工を営む者が、通信機器(事務所用電話主装置・電話機)のリース契約を締結した事案につき、控訴人は、専ら賃金を得る目的で1人で印刷画工を行っていたに過ぎず、その規模は零細であったこと、経営困難との理由で、契約締結の約4か月後に廃業届を提出していること、控訴人の事業規模や事業内容からしても、従前から使い続けていた家庭用電話機が1台あれば十分であったといえること、控訴人は事業といっても印刷画工を専ら1人で、手作業で行うような零細事業に過ぎず、かつ、控訴人自身パソコンを使えないというのであって、リース対象の通信機器は、控訴人が行う印刷画工という仕事との関連性も必要性も極めて低いことからすると、当該リース契約は、控訴人の営業のために若しくは営業として締結されたものであると認めることはできないとして、クーリング・オフを認めています。
【東京地裁平成27年10月27日判決】
家族の住む住宅兼店舗で喫茶店を営む個人が電話機、ファクシミリのリース契約を締結した事案につき、被告は喫茶店を経営しているが、被告と妻のみが従事し、一日の来客は三〇人程度で、店舗を利用しているのは地元の固定客であって、電話番号は電話帳に記載していないこと、営業の手段として当該電話機及びファクシミリの有益性は希薄であり、したがって電話の利用は個人的使用が中心であって、ファクシミリも子どものクラブ活動等の連絡に利用しており、業務のために全く利用していないこと、当該リース契約締結の経緯、被告の営業の規模、内容、リース物件の営業使用の必要性や頻度を考慮すると、当該リース契約の契約書等に屋号を記載していること、リース料が被告の営業経費に通信費として計上されていること、インターネット上の飲食店検索サイトの店舗基本情報や、地元の飲食店マップに建物の電話番号が掲載されていることを考慮しても、当該リース契約は「営業のために若しくは営業として」締結したものとは認められないから、特商法の適用除外には該当しないとして、クーリング・オフを認めています。 -
2015.11.30
過払い金の消滅時効
●過払い金の消滅時効はいつから進行するか?
過払い金の消滅時効は、取引が終了したとき、すなわち、最後に借入ないし返済をしたときから進行するというのが判例です(最高裁平成21年1月22日判決)。
但し、この判例は、「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引」に関してのみ、該当するということについて注意が必要です。このような取引においては、取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害になるというべきであり、過払金返還請求権の行使を妨げるものであるから、消滅時効も進行しないというのがその理屈だからです。
最初に継続的な金銭消費貸借契約が締結され、一定の限度額の範囲内で、何度でも借入をすることができる一般的な消費者金融からの借入では、最終取引日から消滅時効が進行すると考えてよいでしょう。
これに対し、継続的な金銭消費貸借取引ではなく、1回の貸付に対し返済がなされているにすぎない場合には、過払金が発生する度に、その都度、消滅時効が進行すると考えられます。他の期限の定めのない債権と同様に、権利発生時から権利行使が可能であり、その行使を妨げる法律上の障害もないからです。
●過払い金の消滅時効期間は、5年か10年か?
10年とするのが判例です(最高裁昭和55年1月24日判決)。
商人間の貸し借りにより発生した過払い金には、商事時効である5年(商法522条)が適用されるようにも思えますが、上記判例は、「利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできないから、その消滅時効の期間は民事上の一般債権として民法167条1項により10年に解するのが相当である。」と判示しています。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
izawa-law.com/ -
2015.05.08
間違って振り込んでしまった場合、どうすればいいですか?
振込金が受取人の預金口座に入金記帳される前であれば、銀行の振込委任業務が終了していませんので、振込依頼人はいつでも、受取人の取引銀行(被仕向銀行)から、振込依頼人が振込を依頼した銀行(仕向銀行)に対する返金手続き(これを「組戻し」といいます)をとることができます。
また、振込金が受取人の預金口座に入金記帳されてしまった後でも、受取人が誤振込であることを認め、組戻しを承諾している場合には、組戻しに応じるのが銀行実務です。
この点、名古屋高裁平成17年3月17日判決(金融・商事判例1214号19頁)が参考になります。同判決は、振込依頼人が、誤振込を理由に仕向銀行に取戻しを依頼し、受取人も、誤振込による入金であることを認めて、被仕向銀行による返還を承諾している場合には、正義、公平の観念に照らし、その法的処理において、(法的には、預金契約が成立しているが、)実質は受取人と被仕向銀行との間に振込金額相当の預金契約が成立していないのと同様に構成し、振込依頼人の被仕向銀行に対する、直接の不当利得返還請求を認めています。
では、受取人が組戻しを承諾しない場合にはどうすればいいかというと、この場合には、振込依頼人から、受取人に対し、不当利得返還請求権に基づき、返金の交渉ないし訴訟によって解決するしかありません。
なお、受取人が誤振込があることを知りながら、その情を秘して、被仕向銀行に対し預金の払戻しを請求することは詐欺罪にあたるというのが最高裁判例(平成15年3月12日判決)ですので、これを指摘して交渉してもよいでしょう。
霞ヶ関パートナーズ法律事務所
弁護士 伊 澤 大 輔
☎ 03-5501-3700
izawa-law.com/
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2021年 (4)
-
2015年 (2)

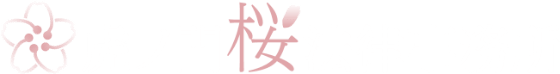
![[受付時間]平日 9:00〜17:30 03-6432-0965](/wp-content/uploads/contact_tel.png)